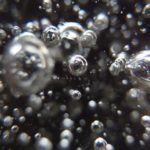自然(感性)は至ることろで合一し、知性は至るところで区分するのです。そしてさらに理性が再び合一するのです。したがって人間は哲学をしはじめる以前のほうが、その研究をまだ完了していない哲学者よりも真理に近いのです。 (第18信)
(参考:法政大学「人間の美的教育について」フリードリヒ・フォン・シラー著、小栗孝則訳)
時々、思う。
どうして、みんなこの世界のことを知っているかのように生きているけれど、どこでそれを知ったのだろう? と。
私たちは、この世界のことや生きることについて、誰かがこうだと言ったことをただそのまま信じているだけではないだろうか。その点で、まだどんな人の考えも教えられていない子供たちは、大人たちよりも多くのことを知っている、と言えるのではないだろうか。
社会が見せる世界を信じて疑わない大人が、自分を通して自分の言葉に変換することもなく「世の中とはこうゆうものだ。こうゆう生き方をしなければいけないのだよ」とそのまま教えると、子供はどうなってしまうだろう?
子供は、大人と同じことをする。大人が(親が)間違っているなんて、信じたくない。感性の強い子であれば、その言葉のむなしさに気づくかもしれないけれど、大人を傷つけないように自分の思いはしまっておいて、大人の言う通りの振る舞いをするかもしれない。でも、知ったかぶりの大人はそれにも気づかずに、同じ言葉を繰り返していく・・・。
「子供の気持ちがわからない」ということを聞くけれど、誰でも子供だったのだから、その時自分がどんな気持ちでいたのか、どうして欲しかったのかを思い出せばいいのに、と思う。大人たちの言葉に違和感を覚えたことはなかっただろうか。大人たちのことをどう見ていただろう・・・?
私は、「なんだ。大人も知らずに生きているんだ」とわかったとき、これからは自分で学ぼうと思うようになりました。
大人ぶってる大人ほど“本当の大人”とは程遠く、「よく子供っぽいって言われるんだよ」と、“本当の子供”のことをよくわかりもせずヘラヘラしている大人を見ると、ため息が出てしまう。「私は何でも知っている」そんな人ほど、知らないことが多かったのです。そして、そういう大人は、「子供は何も知らない、何もできない」と思っているのです。
大人が言う「知っている」は、一体何を知っているのだろう?
それは「世の中とはこうゆうものなんだ」と言われていることを覚えることだろうか。何かをすることが、「自分がそうしたいから」ではなく、「世間に認められるには」という考え方になることだろうか。
自分で自分の生き方を考えるより、誰かの、みんなの言うことに乗っかった方が楽だし、仲間外れにされるのは嫌だし、私にそんな力もないし・・・。と言いながら。
変わらなくてはいけないのは、知っているフリをしている大人の方なのではないだろうか。
「知らない」ということで、人や自然を傷つけてしまうこともある。
「自分にはまだまだ知らない事がたくさんある」と認めると、そこにスペースができて視野がグッと広がり、凝り固まった思考は柔軟になり、いろんな考え方があることを知ることができ、そうやって知識も経験も増えていく。
そして、「答えはいつも自分の中にある」と認めると、自分自身の深く高いところにアクセスすることができ、そうすると、誰かの言葉に乗っかったり、外側で起きることに反応するのではなく、自分の内側に注意を向けるようになる。そして、世界は目に映る外側の世界だけで起きているのではないのだと気づき、舵を握っているは自分なのだと、世界に対して責任をもつようになる。
自分の世代と次の世代が、全く同じ考え方であることは限らない。
正しいとされていたことが正しくなくなる、ということは多々起きていることではないだろうか。
それなのに、疑うこともなく上が言っているのだからと、次の世代へ次の世代へと同じ考えを押しつけていくのは、窮屈で不自然に感じる。
前の世代のことをすべて否定してもいい、と言っているわけではありません。先人の言葉には、閉じてしまった感覚を蘇らせてくれる言葉や普遍的な考えはたくさんあります。
そして、次の世代の言葉をすべて受け入れるべきだ、と言っているわけでもありません。経験不足による間違いや、感情にまかせた短絡的で一方的な考えをするのも若者です。
どの言葉に共鳴するのかによって、今、自分がどの段階にいるのかを知ることもできるかもしれません。
この世界で、子供たちが生き生きと成長できるようにするには、何をしたらいいだろう?
「子供を守る」とは、何を守ることなのだろう。守ると言いながら、抑えつけてはいないだろうか。
本当の教育とは、“与えることではなく引き出すことなのだ”という言葉がある。
「こうしなければいけない。こうゆう生き方が正しい」と囲って縛りつけるのではなく、「自分が得意なことは何なのか。本当の望みは何なのか」と内側から解放してあげる方が、ずっと自然なことで、それができる大人がステキな大人なのではないだろうか。
私たちは、“この世界でどんな経験をしたいのか、それを達成するために必要なこと(得意なこと、不得意なことなど)は何なのか、そういうことを生まれてくる前に全部自分で決めてきた”という言葉がある。
そうだとしたら、自分と他人を比べて不平不満を言うのはおかしなことだし、目的はみんな違うのだから、自分以外の人の生き方に対して批判をしたり、ましてコントロールしようとするなんてこともできないはず。
個性は、はじめからもって生まれてくるものだから、否定したり無理に作り出したりせず、受け入れ、互いに認め合うことができれば、自分の考え方や経験も広がって、豊かに楽しく生きていけるのではないだろうか。
いろいろな物語を読んでいると、大人と子供の対比がよく書かれていることに気づく。
そこには「大人とはこうだ。子供とはこうだ」と決めつけ、大人の方が優位であるとし、いつも不満を持ちながら自分の得になること以外は追い払う、というような大人と、子供のことを「何も知らない、何もできない人」だとみることはなく、同等に接し、何よりも“子供である”ということを尊敬し、どんなことでもまず静かに話を聞き、相手の力を引き出すようなアドバイスをして送り出してくれるような大人の二パターンが描かれている。
どちらが、“本当の大人”だろう?
ル=グインは、“成熟した大人”という言葉を使って、こう言いました。
成熟とは伸び越えて別物になることではなく、成長することだとわたくしは思います。大人とは<死んでしまった子ども>ではなく、<生きのびえた子ども>なのです。成熟した大人のもつすぐれた能力はすべて子どもに内在するとわたくしは信じていますし、若いうちにそれを大いに励まし伸ばしてやれば、大人になってから正しく賢明にそれを働かせることができるようになる、逆に子どもの頃抑圧し芽をつみとってしまえば、大人になってからの人格も矮小なゆがんだものになってしまうと思います。
(参考:サンリオSF文庫「夜の言葉 <アメリカ人はなぜ竜がこわいか>」アーシュラ・K・ル=グイン著、スーザン・ウッド編、山田和子・他訳)
ミヒャエル・エンデはこう言いました。
これまでの生涯を通じて、今日、本当の大人と称されるものになることを、わたしは拒みつづけてきました。つまり、魔法を喪失し凡庸で啓蒙された、いわゆる“事実”の世界に存在する、あの不具の人間たちです。そして、このとき、わたしはあるフランスの詩人が言った次の言葉を思い出します。まったく子どもでなくなったときには、わたしたちはもう死んでいる。
まだ凡庸になりきらず、創造性が少しでも残る人間なら、だれのなかにも子どもは生きていると、わたしは思います。偉大な哲学者、思想家たちは、太古からの子どもの問いを新しく立てたにほかならないのです。わたしはどこから来たのか? わたしはなぜこの世にいるのか? わたしはどこへ行くのか? 生きる意義とは何なのか? 偉大な詩人や芸術家や音楽家の作品は、かれらのなかにひそむ、永遠の神聖な子どものあそびから生まれたものだと思います。九歳でも九十歳でも、外的な年齢とは無関係に、わたしたちのなかに生きる子ども、いつまでも驚くことができ、問い、感激できるこのわたしたちのなかの子ども。あまりに傷つきやすく、無防備で、苦しみ、なぐさめを求め、のぞみをすてないこのわたしのなかの子ども。それは人生の最後の日まで、わたしたちの未来を意味するのです。(参考:岩波書店「エンデのメモ箱 <永遠に幼きものについて>」ミヒャエル・エンデ著、田村都志夫訳)
幼稚な大人はかっこ悪いけど、子供らしさを失っていない大人は、頼もしく思える。
大人の言う「知っている」を、手放してみませんか?
そこで、あなたは何を手に入れるだろう? 作り上げた大人でいることをやめたとき、あなたは何になるだろう?
子供たちの言葉に、耳を傾けてみませんか? そのとき、輝く真の現実が、再び目の前に広がるでしょう。
「たいへんだ! 隠者がおれたちを追いかけて、海の上を陸地のように走っている。」乗客たちはそれを聞くと、起きあがり、みんな船尾に走り寄った。隠者たちが手をつなぎあって走っているのを、みんなが見た。両端の者が手をふって、とまれと合図をしている。三人がみんな陸地のように、海の上を走っているが、足は動かさない。
船をとめる間もないうちに、隠者たちは船とならんで、ふなべりのすぐ下に近づいた。そして、顔を上にむけると、声をそろえていいだした。
「忘れてしまいました。あなたが教えてくれたことを忘れてしまったんです。くりかえしているうちは、おぼえていたのに、一時間ほどくりかえすのをやめたら、言葉が一つぬけ、忘れてしまって、全部めちゃくちゃになってしまったんです。なに一つおぼえていません。もう一度教えてください。」
高僧は十字を切り、隠者たちのほうに身をかがめて、いった。
「あなたたちの祈りこそ、神様までとどいているのです、隠者のみなさん。わたしはあなたたちを教えるような者ではありません。われわれ罪深い者のためにお祈りをしてください!」
そういうと、高僧は、隠者たちにむかって深々とおじぎをした。すると、隠者たちは立ちどまり、くるりとうしろをむき、海を通って帰っていった。そして、隠者たちが去っていったほうから、朝まで光が見えていた。(参考:福音館書店「トルストイの民話」レフ・ニコラエヴィッチ・トルストイ作、藤沼貴訳)